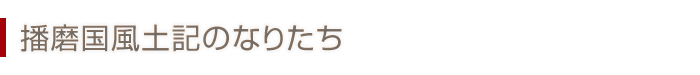
「播磨国風土記」は姫路でまとめられた
「播磨国風土記」の編纂、提出には、
現在の姫路に置かれていた播磨国府(国庁)につとめる国司があたりました。
■播磨国府跡
国府とは、奈良・平安時代に、国司が仕事をした国庁や、その他の役所、官舎などが置かれた都市です。
播磨国府の位置は、発掘調査で出土する奈良時代の遺物の様子などから、現在の姫路郵便局付近を中心とし、姫路城跡周辺から姫路駅付近にかけての範囲に各種の役所の建物が点在していたと思われます。
■播磨国司
国には、人口や耕地面積の多少などによって、大・上・中・下の四つの等級があり、それによって役人の定員が決まっていました。
播磨は大国であり、正規職員である国司は9名、雑務に従事するその他の職員は534名と定められていました。
中央政府に任命された播磨国司は、守(かみ)1名、介(すけ)1名、掾(じょう)2名、目(さかん)2名、史生(ししょう)3名。
任期は4~6年。その国の一般行財政はもちろん、軍事・司法・宗教・交通の全般に及ぶ仕事をしました。
風土記編纂にあたった播磨国司の候補として挙げられるのは、守の巨勢朝臣邑治(こせのあそんおおじ 生年不明- 神亀元(726)年)、石川朝臣君子(いしかわのあそんきみこ)、大目の楽浪河内(さざなみのかわち)、の3人です。
○巨勢朝臣邑治は、大宝2(702)年から慶雲4(707)年まで遣唐使として唐に派遣された人で、和銅元(708)年に播磨守に任ぜられました。
○石川朝臣君子は、霊亀元年(715)に播磨守に就任。
万葉集で播磨娘子(はりまのおとめ)から歌を贈られた石川大夫(いしかわのまえつきみ)はこの人物と考えられています。
石川大夫の任を遷さえて京に上りし時に、播磨娘子の贈れる歌二首
絶等寸の 山の峯の上の 桜花 咲かむ春べは 君し思はむ (巻9-1776)
君なくは なぞ身装餝はむ 匣なる 黄楊の小櫛も 取らむとも思はず (巻9-1777)
○楽浪河内は和銅5(712)年当時に播磨大目であったことがわかっています。
百済からの渡来人である父をもち、文学的素養の高い官人です。
神亀元(724)年以降は、高丘連(たかおかのむらじ)を賜り、天平18(746)年に伯耆守に任じられます。
また、万葉集に二首を残しています。歌の内容から、大伴家持とともに恭仁京に居たときのものと考えられています。
故郷は 遠くもあらず一重山 越ゆるがからに 思ひぞ我がせし (巻6-1038)
我が背子と ふたりし居れば 山高み 里には月は 照らずともよし (巻6-1039)
